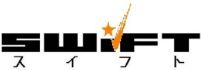コラム
column
土砂災害対策工事 | 効果が高い施工事例を紹介
2025年08月11日
年々深刻化する豪雨や台風被害により、土砂災害のリスクが全国で高まっています。
そうした中で、地域の安全を守るために欠かせないのが「土砂災害対策工事」。
本記事では、実際の施工事例を交えながら効果的な対策方法や工法のポイントを解説します。
これからの防災対策の参考に、ぜひご一読ください。

土砂災害対策工事の基本と背景
土砂災害は、豪雨や地震などにより突発的に発生し、多くの人的・物的被害をもたらします。
近年、気候変動の影響で豪雨の頻度や規模が増加しており、土砂災害リスクもさらに高まっています。
そのため、土砂災害対策工事は、地域の安全確保と持続的な社会発展を支える重要なインフラ整備の一環として位置づけられています。
土砂災害が発生しやすい主な原因
土砂災害が発生する主な原因としては、集中豪雨や台風による大量の降雨、地震活動による地盤の弱体化、さらには急傾斜地や脆弱な地質条件の存在などが挙げられます。
また、森林伐採や土地開発による自然環境の変化も地盤の安定性を損ない、災害リスクを高める要因となります。
これらの複数要因が重なった場合、土石流やがけ崩れ、地すべりなどの大規模な被害が発生しやすくなります。
施工工法選定のポイントと考え方
土砂災害対策工事の施工工法を選ぶ際には、現場の地形や地質条件、災害発生の頻度や規模、さらには周辺環境への影響やコストなど多角的な要素を総合的に判断することが重要です。
例えば、斜面の形状や規模、地盤の強度、雨水の排水ルートを詳細に分析し、最適な工法(擁壁工、法枠工、グラウンドアンカー工など)を選定します。
また、設計段階から将来的な維持管理も考慮し、長期的な安全性を確保できる計画が求められます。
現場別に採用された効果的な土砂災害対策工事例
現場の特性に応じた多様な土砂災害対策工事が全国各地で実施されています。
たとえば、急峻な山間部では落石防護柵や砂防堰堤が設置され、市街地周辺では擁壁や地下排水設備が用いられます。
また、地すべり多発地帯では地中アンカーや排水ボーリングを活用した工法が採用されるなど、現地調査や過去の災害履歴をもとに最適な対策が計画されています。
これらの事例は安全性向上と周辺環境保全の両立が図られています。
地形や地質による工法の使い分け
土砂災害対策工事では、地形や地質による最適な工法の選択が安全確保の鍵を握ります。
傾斜が急な山地ではコンクリートの擁壁やロックネット工が効果的であり、緩やかな斜面や粘土質地盤ではグラウンドアンカーや杭基礎などが選ばれやすいです。
また、透水性の高い地域では排水工の強化が重要となるほか、地盤の安定性が低い場所では土留工や土壌改良も必要とされます。
実際の選定には専門家による詳細な地質調査が不可欠です。
予防的観点からの事前施工事例
土砂災害は発生してからの対応だけでなく、発生を未然に防ぐための予防的対策が重要です。
多くの自治体や地域社会で、定期的な斜面安定調査や雨水流路の整備などが事前施工として取り組まれています。
たとえば、大雨時の水流増加を想定した排水溝の増設や植生による斜面の緑化・保護などのソフトとハードを合わせた総合的対策が進められています。
これにより、災害発生の確率を大きく低減することが可能となります。
土砂流出を防止した最新工事のポイント
最新の土砂災害対策工事では、ICT(情報通信技術)の活用や環境配慮型材料の導入が進んでいます。
たとえば、リアルタイムの斜面挙動モニタリングシステムや植生工を取り入れた自然再生型工法などが注目されています。
さらに、現場管理の効率化や施工精度向上のため、ドローンや3D測量技術も導入されています。
これらにより、土砂流出を徹底的に抑制しつつ、周辺環境へのインパクトも最小限にとどめる工事が可能となっています。
緊急対応における応急工事の実例
突発的な豪雨や地震などにより土砂災害が発生した際には、被害拡大を防ぐため迅速な応急工事が求められます。
過去の実例では、土のうやブルーシートを用いた仮設対策、応急ダムや排水路の即時設置が功を奏したケースがあります。
また、被災地のアクセス確保や避難路の安全確保のため、仮設道路や橋の設置も行われました。
このように、限られた時間と資材の中で最大限の効果を発揮する現場対応能力が必要不可欠です。
工事後のメンテナンスと再発防止の取り組み
土砂災害対策工事が完了した後も定期的な点検・メンテナンスを継続し、老朽化や予期せぬ損傷を早期に発見・修繕することが重要です。
また、土地利用の変化や気候変動を踏まえた再評価・再設計も必要となる場合があります。
加えて、地域住民への防災教育や避難訓練などソフト面の取り組みも強化されており、ハード・ソフト両面での再発防止に力が入れられています。
公共工事と民間工事、それぞれの特徴
土砂災害対策工事は、行政主導の公共工事と個人や企業が実施する民間工事に大別されます。
公共工事は広域的かつ継続的な対策が可能で、地域全体のインフラ保護や住民の安全を確保する役割があります。
一方、民間工事は個別ニーズに応じたきめ細かな対応ができ、民地での安全確保や土地資産の保護に寄与します。
それぞれの特徴を生かし、官民連携による総合的な災害対策が今後ますます重視されています。
まとめ|災害リスクを低減するための取り組みの重要性
土砂災害リスクを低減するためには、個々の現場特性を正確に把握し、対策工事の設計・施工・メンテナンスまで一貫した取り組みが重要です。
さらに、予防的対策や情報技術の導入、社会全体での多層的な対策が必要とされています。
これらの取り組みによって、今後も持続可能で安全な社会基盤の構築が期待されています。