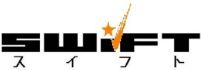コラム
column
電線共同溝に地上機器を活用した無電柱化が今なぜ必要とされているのか
2025年09月11日
地震や台風などの自然災害が増える中、都市の安全性と景観の向上を目的に「無電柱化」が全国で進められています。
中でも、歩道下に電線を通す「電線共同溝」と、地上に機器を配置する新たな手法を組み合わせた無電柱化が注目を集めています。
なぜ今、こうした取り組みが必要なのか?本記事では、無電柱化の背景と課題、そして地上機器を活用する最新の無電柱化手法のメリットについて、わかりやすく解説します。

電線共同溝と地上機器について
近年、日本各地で無電柱化の流れが加速しています。
背景には自然災害の多発や都市景観の向上、歩行者の安全確保などがあり、従来の電柱や架空電線に頼った電力供給インフラに見直しが迫られています。
特に電線共同溝と地上機器の活用は、無電柱化をより効果的かつ効率的に進める上で不可欠な要素となっています。
近年増加する自然災害と電柱リスク
日本では地震や台風・豪雨など大規模な自然災害が頻発しており、その都度、倒壊や損壊した電柱による停電や通行障害が大きな問題となっています。
電柱や架空線は高い位置に設置されているため、倒木や飛来物の被害を受けやすく、被災後の復旧作業にも多くの時間とコストがかかります。
無電柱化はこうした災害リスクの大幅な軽減策として注目され、多くの自治体が取り組みを強化しています。
都市景観の向上と無電柱化
無電柱化は都市の景観を大きく変える要素でもあります。
乱立する電柱や複雑に入り組んだ電線は街並みの美しさを損なうだけでなく、観光地や商業地のイメージダウンにもつながります。
景観を重視したまちづくりを進める上で、無電柱化は欠かせないインフラ整備であり、地域ブランドの向上や観光客誘致にも寄与しています。
電線共同溝とは何か
電線共同溝とは、道路などの地下に設けられる管路やトンネルのことで、電力線や通信線、ガス管など複数のインフラを集約して収容する構造物です。
これにより、複数の企業や事業者が同じ空間を共有でき、工事や保守の効率化が図られます。
また、地上から電線が無くなることで、災害対策や景観形成にも大きく貢献します。
無電柱化における地上機器の役割
電線共同溝による無電柱化においては、全ての機器を地下に設置することは難しく、変圧器や分岐盤など一部の設備は地上に設置する必要があります。
これらの地上機器は、電気や通信の制御、保守点検、非常時の対応を担い、地下インフラの機能を補完する重要な役割を果たします。
合理的に配置することで無電柱化の推進が実現します。
地上機器を活用することで得られるメリット
地上機器を効果的に活用することで、無電柱化のコスト削減や保守作業の簡便化というメリットが生まれます。
地下空間の限りあるスペースを補い、変圧器や通信機器の点検や修理も地上で行えるため、作業効率が向上します。
また、自然災害時には迅速な復旧が期待でき、インフラの信頼性と安全性を同時に高めることが可能となります。
地上機器導入に伴う新たな課題
一方で、地上機器の設置には新たな課題も生じます。
歩道上にスペースを確保する必要があるため、通行スペースの確保や景観への配慮、犯罪のリスク(侵入やいたずら防止)など、計画段階から十分な検討が求められています。
また、維持管理コストや各種制度との整合性も、地域によっては調整が必要になります。
日本国内での無電柱化推進政策
国や自治体は無電柱化の推進に向け、関連法規の整備や補助金制度の充実に取り組んでいます。
2020年には無電柱化推進法も施行され、緊急輸送道路や重要インフラ周辺では積極的な導入が進められています。
国土交通省により2021年に策定された「無電柱化推進計画」では、緊急輸送道路や災害対策を優先する方針が示され、今後5年間で約4,000kmの整備着手を目標としています。
市街地開発事業に伴う無電柱化では、設計・施設整備費に対して国から補助が行われる「まちづくり促進事業」も導入されています。
今後はさらに効率的な推進体制の構築や、地上機器の標準化、住民への理解促進も重要な課題です。
災害時のレジリエンス向上と無電柱化
無電柱化は災害時の都市レジリエンス向上に直結します。
地下化によって電力供給や通信の途絶リスクが減り、緊急車両の通行や避難経路の確保も容易となります。
特に災害多発地域では、インフラの強靭化が社会的な要請となっており、無電柱化の価値は今後ますます高まっていくでしょう。
これからの都市づくりに求められるインフラ整備の方向性
今後の都市づくりでは、日常の快適さだけでなく、災害時の強靭性や環境への配慮も重要視されます。
無電柱化や電線共同溝・地上機器を含めたインフラ整備の在り方は、スマートシティの実現や持続可能な都市の創造につながります。
既存の都市インフラを見直し、地域ごとの課題や特色に応じたインフラ戦略が求められる時代が到来しています。