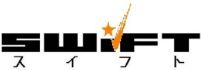コラム
column
液状化の地盤対策 | 施工費用や地震後の対応フローを解説!
2025年11月08日
液状化は地震時に土が液体のように変化し、建物や道路に大きな被害を与える現象です。
特に埋立地や軟弱な砂地では被害リスクが高く、住宅やインフラの安全確保のために、あらかじめ地盤対策を行うことが不可欠です。
本記事では、液状化の基礎知識や被害判断のポイント、施工費用の目安、さらに地震後の初期対応や専門家への依頼フローまで詳しく解説します。
これを読むことで、液状化リスクに備えた計画的な地盤対策の進め方を理解でき、安心して暮らせる環境づくりに役立てることができます。

液状化の地盤対策について
液状化は地震時に起こる地盤の現象で、土が液体のように振る舞うことで建物や道路に深刻な被害を及ぼす可能性があります。
そのため、新築や既存住宅の耐震補強を検討する際には、液状化リスクを正しく理解した上で地盤対策を行うことが重要です。
液状化の基礎知識
液状化は砂質土や締固めの不十分な地盤で発生しやすく、地震の揺れによって土粒子間の水圧が上昇し、土自体が液状に変化します。
これにより建物が傾いたり、基礎が沈下したりする危険性があります。
特に埋立地や川沿いの軟弱地盤はリスクが高く、地震時の液状化マップや過去の災害記録を確認することが第一歩です。
さらに、地盤調査ではボーリングや標準貫入試験を行い、土の種類や締め固まり度、水位などを測定することで液状化の可能性を科学的に評価できます。
被害の判断基準
液状化による被害は、建物の傾き、ひび割れ、地下配管の浮きなどで判断できます。
一般的には基礎の沈下が50mm以上、または傾斜が2度以上の場合は重大な影響があるとされます。
道路や駐車場では地盤の亀裂や陥没、水たまりの発生が目安となります。
また、液状化による被害は目に見えない場合もあるため、専門家による地盤調査や地震履歴の分析も併せて行うとより正確にリスクを判断できます。
工法の選定ポイント
液状化対策には複数の工法があります。
代表的なものは「表層地盤改良」「深層混合処理」「杭基礎補強」などです。
表層地盤改良は比較的浅い層の強化に向き、施工費も抑えられます。
深層混合処理は軟弱地盤の深い層まで安定化させる方法で、住宅地や公共施設でも採用されます。
杭基礎補強は建物を安定した深い地盤に支持する手法で、大規模建物や重要施設に適しています。
選定の際は建物の種類、地盤の深さ、施工コスト、周辺環境への影響などを総合的に判断することが大切です。
費用の概算方法
液状化対策の費用は工法や施工規模、地盤条件によって大きく異なります。
目安として、表層地盤改良は1平方メートルあたり1万〜2万円程度、深層混合処理は2万〜4万円程度、杭基礎補強は1本あたり数十万〜100万円以上になることもあります。
概算費用を出す場合は施工面積や杭本数、重機や材料費を計算し、現地調査報告書を参考にすると精度が高まります。
また、行政によっては液状化対策に補助金や助成制度を活用できる場合もあるため、併せて確認することが重要です。
地震後の対応フロー
地震発生後は被害状況を早期に把握し、適切な対応を行うことが安全確保の第一歩です。
液状化による地盤被害は、放置すると建物の損傷が拡大する可能性があるため、迅速かつ計画的なフローを押さえておくことが必要です。
ここでは初期確認の手順、専門家への依頼基準、補修と再評価の流れについて解説します。
初期確認の手順
まず地震直後は、建物の傾き、ひび割れ、地面の亀裂や液状化による泥の噴出などを目視で確認します。
次に家屋内の床の傾斜や家具のズレ、水道・ガス管の異常もチェックします。
危険がある場合は立ち入らず、写真やメモで記録して後で専門家に提出できるようにしておくと、被害評価の精度が上がります。
専門家への依頼基準
初期確認で建物や地盤に異常が見られた場合、土木技術者や建築士、地盤調査の専門会社に依頼します。
具体的には、建物の傾きが2度以上、沈下が50mm以上、基礎周りの亀裂や配管の浮きが確認された場合は速やかに専門家評価を行うことが推奨されます。
また、自治体による災害対策支援や補助制度を活用することで、費用負担を軽減できる場合もあります。
補修と再評価の流れ
専門家による調査の結果、液状化対策工事が必要と判断された場合は、工法選定、施工計画、施工後の再評価という流れで進めます。
施工後は地盤の安定性や建物の傾き、ひび割れの状況を再度確認し、必要に応じて追加補強やモニタリングを行います。
このプロセスを踏むことで、安全性を確保しつつ将来的な液状化リスクを低減することができます。
この記事で押さえておくべき要点
液状化対策では、まず地盤や地域のリスクを理解し、被害の判断基準を明確にすることが重要です。
工法選定や費用の概算も事前に把握しておくと、計画的な対応が可能になります。
さらに、地震後の初期確認や専門家への依頼、補修・再評価のフローをあらかじめ知っておくことで、被害の拡大を防ぎ、安心して生活を維持することができます。
地盤対策は建物の安全だけでなく、家族や資産を守るための重要なステップです。