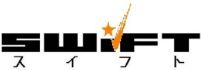コラム
column
ダムと堰堤の違いは?目的や役割など分かりやすく解説します!
2025年04月18日
私たちの生活や自然環境を守るために欠かせない「ダム」と「堰堤(えんてい)」。
どちらも川をせき止める構造物ですが、その目的や規模、役割には大きな違いがあります。
この記事では、「ダム」と「堰堤」の違いを初心者にもわかりやすく解説し、それぞれが果たしている重要な役割についてご紹介します。

ダムと堰堤の違いについて
ダムと堰堤は、どちらも水をコントロールするための構造物ですが、両者の目的や構造において明確な違いがあります。
この違いは歴史的背景や各構造物の設計によるものであり、現代社会においてもその機能は非常に重要です。
ダムと堰堤の基本的な定義
ダムとは、川や谷を横切る形で建設される大型の構造物で、大量の水を貯める目的で作られます。
これに対して堰堤は、河川の水流を制御するための低い構造物で、主に水深の維持や農業用水の確保に用いられます。
ダムは主に発電や洪水調節、人為的な湖の形成に寄与する一方で、堰堤は日常的な水利用に貢献しています。
ダムと堰堤の歴史的背景
ダムの歴史は古代文明にまで遡り、古代エジプトのナイル川沿岸や中国の黄河の周辺で、洪水対策や農業のために利用されてきました。
一方、堰堤は中世ヨーロッパにおいて水車の動力源として重要な役割を果たしました。
どちらも地理的条件や技術の進歩に伴い、その形態を変化させながら発展してきました。
それぞれの主な目的
ダムの主な目的は、発電用の水力エネルギーの生成、洪水の防止、農業や都市部への水の供給にあります。
特に洪水調節や干ばつ時の貯水能力は、地域社会にとって大きな利点となっています。
一方で堰堤の主な役割は、河川の流れを抑制し、農業や家庭用水の安定供給を支えることです。
堰堤は川の生態系維持にも重要な影響を与えています。
構造と材料の違い
ダムは一般に、コンクリートやアースフィルなどの堅固な材料を用いて構築され、非常に高い耐久性を持つのに対し、堰堤は木材、石、金属など、地域で入手可能な材料が利用されることが多いです。
この材料の違いは、構築場所や目的によって選ばれます。
ダムの巨大な構造は長期的安全性と大規模な水管理に適していますが、堰堤は短期的かつ地域ごとの要求に応えやすく作られています。
日本国内の主要なダムと堰堤
日本国内には多くの重要なダムがあります。
たとえば富山県の黒部ダムや滋賀県の長浜ダムなどが知られています。
これらは発電や観光資源としても価値があります。
堰堤については、河川ごとに多岐に渡る設置がされており、特に農業用水や水産業において地域の生活を支えています。
各地域で異なる役割を果たしつつ、日本の水管理の基礎を築いています。
ダムと堰堤の役割
ダムと堰堤は、環境保護、産業、日常生活に欠かせない役割を果たしています。
これらの構造物は水力発電や水資源管理において重要な位置を占めており、経済や環境に対する貢献度が高いです。
以下では、それぞれの役割に焦点を当てて具体的に説明します。
ダムの役割
ダムは主に洪水防止、貯水、発電の3つの役割を果たします。
洪水防止においては、河川の急激な増水を調整し、下流地域の安全を守ります。
また、貯水機能によって旱魃時の水供給も行い、安定した水需給に寄与しています。
さらに、大規模なダムは水力発電所として活用され、再生可能エネルギーの供給源としても重要です。
これらの役割は地域経済にも大きな影響を与えます。
堰堤の役割
堰堤の役割は、主に河川の水位調節や農業用水の確保です。
川の水を一時的に貯めることにより、乾季には必要な水量を安定して供給することができます。
農業や水産業において、堰堤は計画的な水の利用を促進し、地域の経済活動を支えています。
また、小規模ながらも河川の生態系維持に貢献し、自然環境と人間活動のバランスを保つ役割も担っています。
まとめ
ダムと堰堤(えんてい)は、どちらも川の水をせき止める構造物ですが、その目的や規模に違いがあります。
ダムは主に貯水や発電、治水、農業・工業用水の供給などを目的とした大規模な施設で、多くの場合、高さ15メートル以上のものを指します。
一方、堰堤は山間部などに設置され、土砂の流出を防ぐ砂防目的や、水流の調整などを目的とした小規模な構造物です。
つまり、ダムは水を「ためる」ことが主な役割であり、堰堤は水や土砂を「とどめたり調整」するのが役割です。
それぞれが異なる環境・目的に応じて設置されており、自然災害の防止や水資源の管理に大きく貢献しています。